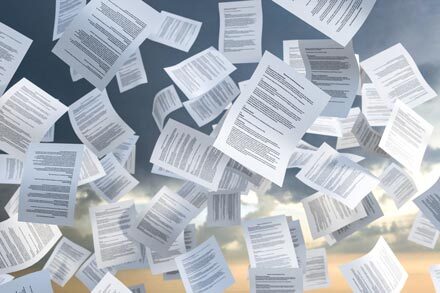情報検索の仕組み
2024/09/04
情報の検索は、皆さんが必要に応じて行っている日常的な行動ではないでしょうか。
現在では、スマートフォンやパソコンで簡単に調べることができる反面、必要な情報を探し出すのは以前よりもむしろ難しくなっていると考える人もいます。その考えの背景として、デジタライゼーションが急激に進行する社会で適切な情報を迅速かつ効率的に入手し、十分に活用することが、より一層求められているからです。
情報検索とは
「情報検索」の定義を見てみると、「あらかじめ組織化して大量に蓄積されている情報の集合から、ある特定の情報要求を満たす情報の集合を抽出する*1)」となっています。
最も簡単な情報検索の例は、アドレス帳で連絡先の電話番号を調べることです。
この場合、情報の集合は知人などの氏名と電話番号であり、連絡先を氏名の音順に並んだリストから照合して必要な情報、すなわち電話番号を取り出すことができます。つまり、アドレス帳では情報が体系的に整理されていて、検索するための手段(ツール)が提供されています。
また「昨年作成されたある業務に関する文書を読みたい」という場合、無作為に積んである文書の中から目当てのものを探そうとすれば、見つかるまで全ての文書に目を通さねばなりません。
情報検索は利用目的をあらかじめ想定し、それに見合った形で情報を整理します。その上で検索のための手段を提供することで実現されるため、このような探し方は情報検索とは呼べません。
- 全文検索
GoogleやYahooなどのサーチエンジンのように、文書の中身そのものが検索対象
文書の中身そのものを検索することができるようにあらかじめ機械的に処理することが可能で、人手をかける必要がない
- メタデータ検索
図書館の蔵書検索システムのように、対象文書のタイトルや著者名など、その文書の文脈や背景に関する情報が検索対象
検索の目的やシステムの利用場面をあらかじめ検討し、検索用のメタデータを整備することで、効率よく検索できる
まとめ
私たちが日頃利用しているインターネットの情報検索や組織内外で利用できるデータベースシステムも含めて、全文検索とメタデータ検索の利点と欠点を考慮し、どちらを用いるのか、あるいは両方を構築するのかを検討する必要があります。
情報検索の仕組みについてさらに詳しく知りたい方は、情報資産管理ポータルサイト「知っているようで知らない? 情報検索の仕組み」をご覧ください。
日本レコードマネジメントでは文書管理に関する様々なテーマや課題について、コンサルティングからシステム開発・運用に至るまで一貫したサービスをご提供しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
*1)日本図書館情報学会用語辞典編集委員会編. 図書館情報学用語辞典. 第4版, 丸善出版, 2013, 284p. より